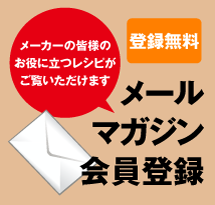【うなぎ】柳ばし
(東京都/大田区)
創業は大正13年(1924年)と90余年もの歴史を誇る老舗。〝うなぎ食堂〟を謳い、うなぎ料理を看板商品としながらも、メニューは刺身や天ぷら、鍋など幅広くとりそろえており、四季折々の味を気軽に楽しむことができます。店構えこそ日常使いのできるうなぎ店ですが、使う食材は国産のうなぎやどじょうの他、ハタ、ハモ、あんこうといった高級魚が並び、本格和食店に劣らぬ高品質で提供しています。
- クローズアップメニュー 1
-

-
うなぎ蒲焼 梅2,000円、竹2,300円、松2,500円、特上3,200円、特特(二串入)4,500円(税抜)(写真は松)
看板商品のうなぎ蒲焼は宮崎産を中心に国産のもの厳選。やや小ぶりなものを選んで若いうなぎの繊細な身のやわらかさと風味が特徴です。創業時から継ぎ足し続け、震災や戦時も守り続けたタレはうなぎの旨みが溶け込んだ奥深い味わいで、関東風蒲焼の王道である三度づけをして、老舗にしか出せない味、香り、照りをつけています。うなぎ蒲焼きは、お酒のつまみに注文するお客様向けには湯煎ができる代々使ってきた重箱で提供。長時間温かい状態を保ち、ふっくらとした食感を味わうことができます。食材だけでなく器にも品質を重視した姿勢を貫いており、重箱は輪島塗というこだわり。なお、白焼きは竹2,000円、うな重はきも吸付きで梅2,500円から用意しています。
- 技のポイント1
-

-
あらかじめ白焼きしておき、注文ごとに蒸し器で蒸します。
うなぎを焼くのは三代目の好男さんの担当で、この道43年の腕前です。仕入れたうなぎは仕込みの段階で串打ちして白焼きしておきます。白焼きは身と皮目の両面を焼きますが、皮目は焦がしすぎると苦みが立って風味を損ねてしまうため、細心の注意を払いながら焼き加減を調節していきます。そして注文が入ると白焼きを蒸し器に入れて15分程度蒸します。- 技のポイント2
-

-
タレは大正13年(1924年)の創業以来継ぎ足したもの
タレは醤油、酒、みりん、砂糖とオーソドックスな作りですが、うなぎをつけるときに流れる油分が加わり、さらに継ぎ足しながら使うことで独自の旨みが醸成されています。タレをいれた坪は蒸し器と焼き台の間に挟み込むように置き、器具から出る輻射熱が殺菌と熟成の役割を担っています。新しく炊いたタレは一斗缶にいれて保存し、熟成させていきます。砂糖が貴重な食品だった創業当時は砂糖の甘みを強調した味でしたが、1990年頃に現代人の嗜好の変化に合わせて甘さを控えていきました。またみりんのグレードを上げるなどをしてタレの風味に上品さが加わりました。
- 技のポイント3
-


焼きの工程はタレに3度つけながら
やわらかく蒸し上がったうなぎにタレをつけて焼き上げます。焼き台はガス式のものを使用していますが、これはうなぎ本来の繊細な風味を引き出すため。炭火独特の燻香を避けてクセのない味わいをめざしています。そうした考えはうなぎの焼き方にも現れています。うなぎに火を当てるのは身の方だけですが、白焼きの時と同様に皮が焦げることで生まれる苦みをできるだけ少なくするための工夫なのです。創業当時から継ぎ足し続けて奥深いコクを持つタレには、うなぎを3回にわけてつけながら焼いていきます。「1度めは色づけ、2度めは味つけ、3度めは香りと照り」と好男さんは語り、1度めのタレつけの後の焼き時間は3〜5分ですが、2度めは1〜2分、3度めは軽く炙る程度と焼成時間を変えて艶やかな飴色に焼き上げます。

-
- クローズアップメニュー 2
-

-
あんこう鍋(1人前)2,400円(税抜、1人前から提供)
あんこうは主に北海道産のもので、8キロ前後の大型のものを仕入れています。ベースとなる鍋汁は白味噌と田舎味噌をブレンド。旨みの柱となるあん肝はつぶしたものとみじん切りしたものを混ぜて玉状にしておき、客席で溶いていくことで視覚的にもおいしさが伝わってきます。野菜は仕入れ状況によって多少変わりますが、取材時は白菜、長ねぎ、水菜、キノコはしいたけ、しめじ、エノキ、木綿豆腐を提供しています。
- 技のポイント1
-


-
あんこうの肝はシンプルな調理で素材の旨みを引き出します
あんこうの肝は酒で洗ったあとにして大きな血管を取り除いてから、小さくカット。全体に塩、酒、少量のコショウをふった後にラップで筒状にくるみ、鬼すだれで成形します。これを蒸し器に入れて約20分間蒸します。蒸し上がったら、粗熱をとった後に冷蔵庫で冷やして保存します。- 技のポイント2
-


-
ベースは白味噌と田舎味噌を合わせて親しみやすい味に
ベースとなる鍋汁は鰹節と昆布からとった二番だしに酒、みりん、醤油。これに白味噌と田舎味噌を入れて溶き、ひと煮立ちさせます。白味噌だけだと甘さばかりが強調されてしまうところを、素朴な味わいの田舎味噌を足すことで親しみやすい味を心掛けています。味噌味ながらあっさりした味わいです。
- 技のポイント3
-


あん肝はみじん切り後に玉状にし、仕上げに溶きいれます
あんこうは身、ヒレ、皮や髄などの部位ごとに切り分けて各部位をまんべんなく入れます。肝は漉して味噌とともに入れたり、鍋肌で炒めてそぼろ状にするところなど地域や店によって様々ですが、つぶしたものとみじん切りしたものを玉状にして仕上げに溶いていくのが柳ばし流。見た目にも贅沢なうえ、みじん切りにしたあん肝が野菜にからんでしっかりとあん肝の旨みを堪能できるのです。
- オススメメニュー1
-

-
こまどじょう鍋 1,000円(税抜)
5〜10月に北海道で獲れるどじょうの若魚のみを使用したこまどじょう鍋。どじょうの成魚を使った柳川鍋は通年で置いてありますが、こまどじょうを提供できるのは秋だけの旬の味です。体長は7〜8cm程度で、身も骨も柔らかく、頭から丸ごと食べられます。クセも穏やかで上品な味わいが特徴です。こまどじょうは仕込みの段階で15分ほど味噌スープで下茹でして臭みとぬめりをとっておき、注文が入ったら浅底の鉄鍋に二番だし、酒、みりん、醤油を合わせた基本の鍋つゆにこまどじょうを入れ、常温から弱火でじっくり煮ていきます。ひと煮立ちしたところで、1本分の刻みネギをたっぷりと投入。さらに煮立ったところで提供します。こまどじょうは、鍋の他に唐揚げや南蛮漬けでも提供しています。
- オススメメニュー2
-

-
のどぐろのお刺身 1,980円(税抜)刺身は豊洲市場(以前は築地市場)から良質な鮮魚を日替わりで仕入れ、のどぐろやハタなどの日替わりで4品前後、まぐろや甘エビなどの定番7品前後を揃えています。たっぷりと脂ののったのどぐろは薄造りと厚切りして炙ったものの2種類に仕上げて、味わいの違いを楽しめる工夫をしています。紅葉などの季節の葉をあしらうなど高級和食店さながらの盛り付けで見た目も美しく、ツマは透明海藻を使ったり、薬味にはワサビではなく紅葉おろしを合わせているなど細かなところでも独自の工夫をしています。
-
- お店紹介
-

-
中央が三代目店主の大津好男さん、右が女将の香代子さん、左が四代目の隆史さん
柳ばしの創業は東京・北区の王子でしたが、第二次大戦の空襲で焼失。大田区蒲田でリヤカーを引いて営業を再開したそうです。戦後の昭和22年(1947年)に現在の大田区雪が谷大塚に店を構えて以来、地域に根づいた店として愛され続けています。東京と神奈川・川崎を通って平塚までを結ぶ中原街道と自由が丘や奥沢につながる自由通りが交差するそばに立地。庶民的な街並みながら、食にこだわりのある富裕層も多く住む住宅街で、親・子・孫の三代にわたって贔屓にしているお客様も多くいらっしゃいます。店内はイスの背もたれには着物の帯を季節ごとに柄を変えて飾りつけて、華やかさを演出。ホールを切り盛りする香代子さんのアイデアで、場所柄、和装好きな女性も多いことからコミュニケーションを深めるきっかけになっているようです。現在は三代目の好男さんがうなぎを担当し、その他の料理や経営面は四代目の隆史さんに継いでいるそう。隆史さんは「大阪竹葉亭」でスタイルの異なるうなぎの調理を学んだ後に、鮮魚居酒屋の「はなたれ」などで腕を磨きました。柳ばしでは、アルコールに合う一品料理を充実させ、日本酒のラインアップを増やすなど客層の間口拡大に務めています。おかげで食事客だけでなく若い世代へお酒の提案をして料理との相性を楽しんでもらうことに成功し、客単価アップを実現しています。
-
- 基本情報
-

店名 柳ばし 住所 東京都大田区雪谷大塚町7-13 電話 03-3720-1544 営業時間 11:30〜14:30、17:00〜21:30(日・祝日〜21:00) 定休日 木曜日、第3水曜日
席数 39席
主な客層 近隣の夫婦、家族連れ、会社員
予算の目安 昼:1,000〜1,200円、夜4,000〜5,000円 1日の客数 60〜70人(昼・夜合計) 開業 1924年(大正13年)
- ※掲載内容は取材時点での情報であり、記事内容、連絡先、営業時間などが変更になる場合があります。