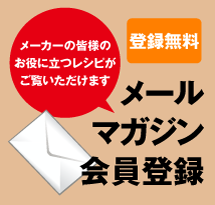(東京都/港区)
創業は寛政三年(1791年)と230年を超える歴史を持つ更科蕎麦の老舗「更科布屋」。観光地としても知られる増上寺門前の大門通りに店を構え、蕎麦好きの常連客だけでなく、近隣会社員、観光客で連日250人もの来店客で賑わいます。伝統の味を守り続ける一方で、時代の変化に合わせて開発されたオリジナルメニューで幅広い客層の支持を得ていることも特筆すべき魅力。今回はそんなオリジナルメニューのひとつである「冷し布屋」についてお聞きしました。
クローズアップメニュー

冷し布屋 1,000円(税込)
二八蕎麦の上にそぼろ、錦糸玉子、キュウリ、カニカマ、刻み海苔を盛り付けたぶっかけスタイルの蕎麦です。六代目店主が戦後急速に普及していった「冷やし中華」をヒントに考案したもので、蕎麦では珍しい彩りと具沢山ぶりが魅力。「更科布屋」伝統の濃厚甘口な蕎麦つゆをかけて食べると、蕎麦ののど越し良さにシャキシャキとしたキュウリやうま味の濃いそぼろが絡まり、食べ応え満点です。
蕎麦粉8割、小麦粉2割で毎朝職人が打つ二八蕎麦は、茹で上げ前で約200gのボリュームで、茹で時間は2分。「切りべら20本(約1.5mm)」と江戸前の標準よりわずか太めに切られた蕎麦は、噛みごたえもしっかりで働き盛りの若者客でも満足度が高い味わいです。 蕎麦粉は、北は北海道から南は沖縄まで時季によって産地を変えながら、常時新蕎麦を提供できる努力をしているのも蕎麦好きを魅了する理由で、風味豊かな美味しさを年間通して楽しめます。
技のポイント1

100年以上受け継がれる「かえし」作りを守り続けています
「更科布屋」の蕎麦つゆは「濃厚甘口」を伝統としています。塩気、醤油、出汁、甘みのすべてが一体となったこってりした甘さがポイント。
同店の味の根幹となる「かえし」は、醤油18ℓに対して砂糖4kgの割合で合わせ、陶器のカメで2週間以上熟成させてから使用します。 100年以上続くこの製法を現在も守り、常温で木製の蓋をしただけの状態で熟成。当然、酸化が進む懸念もありますが、同時に店に付いている「蔵付き酵母」をとりいれて熟成が進むため「この店ならではの味になる」と七代目の金子栄一さんは語ります。
技のポイント2

2種のカツオ節からうま味を出し切るまで炊き上げます
出汁は水18ℓに厚削りのソウダガツオ節と本枯れ節を1対1の割合で計1kg入れ、鍋の中で対流が起きる程度の強火で40〜50分炊きます。
炊いた節を一口かじってうま味が残っていなければ、しっかりと出汁がとれた証。醤油と同じうま味成分のグルタミン酸を含む昆布は使わず、鰹節からとれるイノシン酸を濃厚に抽出してうま味を足し、醤油の塩カドをまろやかにします。
冷し布屋で使う蕎麦つゆはざる蕎麦などと同じもの。かえし1に対して出汁2.5の割合で合わせ、本みりんと砂糖で味を調えてから一晩冷蔵庫で寝かせ、しっかりと味を馴染ませます。 また、かけ蕎麦や鴨南蛮など温かいお蕎麦用の蕎麦つゆはかえしと出汁の割合を1対6を基準にしています。
技のポイント3

合挽き肉のそぼろも砂糖たっぷりに炊いて更科布屋の味を表現
そぼろも、蕎麦つゆの味に合わせたしっかりした甘さが特徴です。合挽き肉1kgを使って一度に約20食分を仕込みます。合わせる調味料は砂糖500g、醤油360ml、清酒180ml、おろしショウガ100g。


合挽き肉は弱めの中火で焦がさないように注意しながら炒めていきます。全体に火が通ったところでいったんザルにとり、脂切りをします。




その後、フライパンに戻して、砂糖、おろしショウガ、醤油、清酒を入れて混ぜ合わせ、中火で10~15分炊いて味を染みこませます。再びザルにとって汁気を切ったら、白胡麻を混ぜて完成。タッパーに移して冷蔵保存します。
注文が入ったら茹で上がった蕎麦を冷水で締めてガラスの器に盛り、出来上がった合挽き肉のそぼろ、錦糸玉子、きゅうり、カニカマ、刻み海苔を盛り付けて完成です。
オススメメニュー1

冷し角煮 1,200円(税込)
大ぶりにカットされた豚角煮が肉々しいオリジナルメニューの一つ。豚バラ肉はかえしを使って煮込むことで、脂の甘さがいっそう引き立つ味わいです。付け合わせはインゲン、白髪ネギ、ワカメ。
オススメメニュー2

月替り 三色そば 1,100円(税込)
取材時は6月の変わり蕎麦である紫蘇切りと、更科蕎麦、二八蕎麦の組み合わせ。一度に3種類の蕎麦が楽しめると、蕎麦好きの常連客を中心に人気です。蕎麦の実の中心部分だけを贅沢に用いて打つ「更科蕎麦」は透き通った白さが特徴で、創業以来続く同店の伝統を今に伝えています。これに3月は桜、7月は笹、12月は柚子といった具合に裏ごしした季節の食材を練り込んだものが変わり蕎麦です。日本の四季の移り変わりを楽しめるのも人気の理由です。
オススメメニュー3

そば豆腐 600円(税込)
蕎麦粉を豆乳と出汁で溶いて片栗粉で固めた自家製の蕎麦豆腐。輪切りキュウリの上におろしわさびを盛り、ざる蕎麦用の辛汁をかけて食べます。少し固めながら舌でつぶせる程度で、口の中で蕎麦の香りが柔らかく広がります。一房の蕎麦を手びねりして素揚げした揚げ蕎麦のカリっと軽い塩気とは好対照で、酒のお供として人気。同品を必ず注文する常連客も多いそうです。また、冬は同品を温かい蕎麦つゆに入れて「揚げ出し蕎麦豆腐」として提供しています。
お店紹介

七代を数える布屋萬吉の後継として修業中の金子雄一さん。「近年はインバウンド客も増加中。海外にも更科蕎麦の魅力を発信していきたい」と意欲を語る。
江戸時代後期の1791年に信州の反物商人だった布屋萬吉が、隅田川のほとり(今の東日本橋)に蕎麦店を開業したのが「更科布屋」の始まり。その後、大正2年(1913年)に四代目 布屋萬吉が店を現在の場所に店を移転し、現在は七代目である金子栄一さんが暖簾を守っています。
江戸前の蕎麦つゆも地域によって異なるそうで、肉体労働者が暮らす下町では塩辛いつゆが好まれましたが、商人が主客層の都心では当時贅沢品だった砂糖の甘さが好まれたことから、同店独特の濃厚甘口の蕎麦つゆが誕生したとか。「お客さまはこの味が好きだから当店にいらっしゃる。他のお店も同様で、店ごとに個性があってお客さまが好みの味を選べるから共存できるわけです」と七代目。材料となる醤油など調味料の味も時代とともに変化するため、適宜メーカーと連絡を取り合ってレシピの調整を施しながら「伝統の味」を守っています。
他方、今回紹介した「冷し布屋」や「冷し角煮」をはじめとするオリジナルメニューが多彩なのも同店の魅力。海老の天ぷらをバットに、茹で玉子をボールに見立てた「野球」や、板状にカットして素揚げした蕎麦をクラッカー代わりに明太子クリームチーズをディップして食べる「そば板カナッペ」など、老舗の味の一言では表しきれないところが、同店の魅力の一つです。
2019年からは金子雄一さんが跡継ぎとして加わり、更科蕎麦の技術と文化が受け継がれています。
基本情報

| 店名 | 更科布屋 本店 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝大門1-15-8 |
| 電話番号 | 03-3436-3647 |
| 営業時間 | 平日11:00~20:30(16:00~17:00中休 L.O.20:00)、土曜11:00〜19:30(L.O.19:00)、日曜・祝日11:00〜19:00(L.O.18:30) |
| 定休日 | 無休(年始年末の特別休業あり) |
| 席数 | テーブル席56席、座敷個室3部屋26席、テーブル個室1部屋10席 |
| 主な客層 | 近隣会社員、昔からの常連客、近年はインバウンド客も増えている |
| 予算の目安 | 1,500円 |
| 創業 | 1791年 |
| HP | http://www.sarashina-nunoya.com/ |
※掲載内容は取材時点での情報であり、記事内容、連絡先、営業時間などが変更になる場合があります。